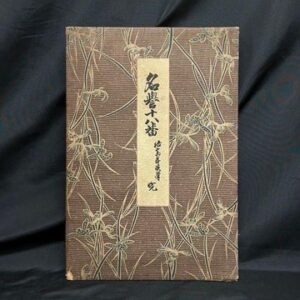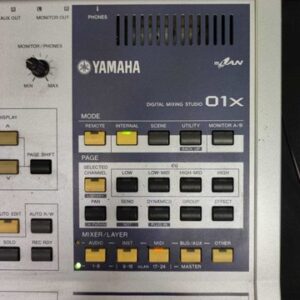生前整理というと、多くの人はまず「物の片付け」や「不用品の処分」など、目に見えるものに意識が向きがちです。しかし、実は見落とされがちなのが「金融口座」の整理です。口座は、故人が残した資産の中でも、発見が遅れれば遺族が受け取ることすらできない重要な存在です。とくに近年では、ネット銀行や証券口座、キャッシュレス決済などが普及し、情報が紙では残されないケースが増えており、これが生前整理の難易度を一段と上げています。家族にとっては、本人しか把握していない口座があるだけで、大きな不安や手間となりかねません。口座の生前整理を行うことは、資産を守り、トラブルを防ぎ、家族に安心を残すことにつながる大切な準備です。
なぜ生前整理で口座の管理が必要なのか?見えにくいリスクを整理する
私たちの生活は、知らず知らずのうちに複数の口座やサービスと結びついています。給与振込のメインバンクに加え、クレジットカードの引き落とし用の口座、投資信託を行っている証券口座、外貨預金や定期預金なども含めると、ひとりの人間が5口座以上を保有しているケースは少なくありません。それに加え、スマートフォンの普及により、楽天銀行や住信SBIネット銀行、PayPay銀行などのネットバンク、さらには暗号資産(仮想通貨)のウォレットや取引口座までもが一般的になりました。
これらの口座は紙の通帳がないことが多く、本人の死後にはまったく気づかれないまま放置されてしまう危険性があります。また、銀行など金融機関では、一定期間利用がない口座を「休眠口座」として扱い、残高の管理が煩雑になることもあるため、放置されることで実質的に資産が失われることもあるのです。故人にとっては大切なお金でも、情報が残っていなければ相続人にとっては「存在すら知らない口座」になってしまう。それが、今の時代特有の口座整理の大きな課題です。
口座の棚卸しを行うには?一つひとつを丁寧に把握する作業が鍵
口座の生前整理を始める第一歩は、「棚卸し」、つまり自分が持っているすべての口座をリストアップする作業から始まります。まずは、通帳やキャッシュカードを引き出しや書類箱から集めてみると、自分でもすっかり忘れていた口座が見つかるかもしれません。定期預金が入っていたまま放置していた口座、昔の勤務先で給与振込用に開設された口座、ネットショッピング用に開いたネット銀行の口座など、その存在を忘れていた口座ほど、死後に家族が把握しづらいものです。
この棚卸し作業では、単に口座名や銀行名を記録するだけではなく、「何のために開設した口座なのか」「現在使っているのか」「残高があるのか」「定期預金の有無や満期日はいつか」といった具体的な情報も一緒に記録しておくことが大切です。できれば、エクセルや手書きの一覧表に「銀行名」「支店名」「口座種別」「用途」「現時点の残高」「最後の入出金日」などを明記し、それに通帳やカードを添えて保管しておけば、万が一の際にも家族が安心して対応できます。
使っていない口座は解約を。判断基準と注意したいタイミング
生前整理の一環として口座を整理する際には、「使っていない口座は思い切って解約する」という考え方が有効です。解約をためらう気持ちもあるかもしれませんが、使わない口座が多ければ多いほど、死後の事務処理は複雑になります。例えば、相続手続きのたびに戸籍謄本や印鑑証明書を用意し、金融機関ごとに違う書類を提出するという作業を、家族は何度も繰り返さなければなりません。
解約を決める際には、「この1年で入出金があったかどうか」が一つの目安になります。もし1年以上動きがないようであれば、今後も使う予定がない可能性が高いので、思い切って解約してしまいましょう。ただし、解約の際に注意したいのが「定期預金」や「外貨預金」など、解約タイミングによって利息がつかなかったり、為替差損が出たりする可能性がある口座です。その場合は、満期まで待つ、あるいは利益を確保してから解約するなど、計画的に進める必要があります。
また、ネット銀行やスマホアプリで完結する口座も増えてきており、それらの口座はログイン情報がなければ解約もできません。IDやパスワードの管理とセットで、解約の準備を進める必要があることも忘れてはいけません。
オンライン口座・証券口座・暗号資産の整理の難しさと対策
インターネットの普及とともに増えたのが、紙の証明書が存在しない「オンライン口座」です。例えば、ネット証券会社で保有している株式、スマホアプリで運用している投資信託、または仮想通貨取引所で保有しているビットコインやイーサリアムなどは、本人の死後にログインできなければ存在すら把握されないという重大な問題があります。
これらのオンライン資産は、相続財産としての価値が高いにもかかわらず、発見されずに放置されることで失われてしまうことが多いのです。家族が証券会社の名前も知らず、IDやパスワードが書かれていなければ、問い合わせすら困難になります。したがって、オンライン口座に関しては「存在の周知」と「ログイン情報の管理」が最も重要なポイントになります。
具体的には、エンディングノートやパスワード管理アプリなどに、オンライン口座のリストとアクセス情報を記録しておきましょう。ただし、セキュリティの観点からも、パスワードそのものをノートに書いておくのではなく、ヒントや保管場所(例:金庫の中にあるUSBなど)を記しておくとより安全です。仮想通貨についても、秘密鍵やウォレットのバックアップ方法を家族に伝える必要があるため、口座以上に慎重に準備しましょう。
エンディングノートに記録する意味と実際の書き方
口座の棚卸しや整理を行ったら、情報をきちんと残すことが不可欠です。その際に役立つのが「エンディングノート」です。エンディングノートは法的な効力こそありませんが、故人の意思や資産の所在を明確にする「情報の伝達ツール」として非常に有効です。紙のノートでもデジタルでも構いませんが、「どこに何の口座があるか」「何に使っていたのか」「どこに通帳・カードが保管されているか」などを記入しておくことで、家族は非常に助かります。
書く内容は、口座情報の一覧、証券や投資の内容、保険や年金の受取情報、また重要な契約(携帯電話、サブスクリプションなど)に至るまで、できるだけ幅広く記載することをおすすめします。そして、そのエンディングノートの存在を信頼できる家族に伝えておくことで、いざというときに迷わず参照してもらえる環境を整えましょう。更新のタイミングとしては、1年に1度見直すことを目安にしておくとよいでしょう。
死後の口座凍結とは?遺族が困らないための知識
人が亡くなると、金融機関がその事実を把握した時点で、故人名義の口座は「凍結」されます。凍結された口座からは出金や振込ができなくなり、遺族であっても自由に使うことはできません。この措置は、資産の不正な引き出しやトラブルを防ぐための正当なものであり、相続人が正式に手続きをしなければ、口座の残高を引き出すことすらできなくなるのです。
手続きには、戸籍謄本や遺言書、印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要になり、銀行ごとに求められる書類も異なるため、複数の口座があると手続きは非常に煩雑です。生前にこれらの口座がまとめられ、用途が明記されていれば、遺族は手続きの優先順位をつけやすくなります。逆に何も情報が残されていない場合、金融機関からの通知や郵便物だけが頼りとなり、時間も労力も大幅にかかってしまいます。
専門家への相談が有効なケースとは?予防の視点で動く
生前整理を進めるなかで、相続税がかかる可能性がある方や、家族構成が複雑な方、海外口座を持っている方などは、専門家への相談が大いに役立ちます。行政書士はエンディングノートの作成や財産目録の支援を行ってくれますし、税理士は相続税の申告や資産の評価、節税対策などをアドバイスしてくれます。弁護士に相談すれば、相続人間の争いが想定される場合の対処や遺言書の作成などについて、法的視点からアドバイスを受けることも可能です。
特に、高齢者が単独で判断しにくいケースでは、第三者の専門家が入ることで、客観的に資産状況を整理し、実行可能な方法を提示してくれます。家族がいても話しにくい「お金のこと」を、冷静かつ中立的な立場で支援してくれることは、大きな安心につながります。
まとめ:今からはじめる「口座の生前整理」で家族に安心を残そう
生前整理において、「口座の整理」は後回しにされがちですが、実は家族の負担を大きく左右する最重要ポイントのひとつです。使っていない口座を解約し、保有しているすべての口座を洗い出して記録するだけでも、大きな一歩となります。オンライン口座や仮想通貨など、デジタル時代の資産管理は本人にしかわからない要素が多く、きちんと記録しておかないと誰にも引き継ぐことができません。
エンディングノートに記録を残し、信頼できる人にその存在を伝えること。必要であれば専門家の力も借りながら、整理を進めていくこと。それが、家族への最高の思いやりであり、自分の人生をきちんと締めくくる準備になります。今すぐ、身近な口座から確認をはじめてみませんか?
買取査定・買取業の開業のご相談はこちら【かいとり隊】
かいとり隊では、不用品や大切なご遺品の買取査定をさせていただいております。
不用品の中には価値判断が難しい品物もございます。
かいとり隊が品物本来の価値を見極めて高価買取いたします。
不用品整理における費用の負担軽減にご活用くださいませ。
また、買取業を始めたいという方も、お気軽に「かいとり隊」までご相談ください!